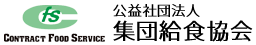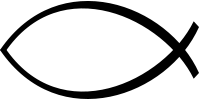vol.3
<最後の晩餐>で何を食べたのか?
「食と宗教」とは深いつながりがあります。よく知られたものに、神道では神事の前に一定期間は肉や魚などを絶つ、仏教でも肉食を戒めることから精進料理が生まれ、イスラム教では豚肉等を禁忌したハラル食品があり、ヒンドゥー教は神聖とされる牛を食べない、と言われています。こうした「食のタブー」とは別に、特定の宗教で定番となる食材や食事もあります。キリスト教に欠かせない食といえば、やはり「パン」と「ワイン」ではないでしょうか。
<そのとき、イエスはユダヤ人に言われた。>「わたしは、天から降って来た生きたパンである。このパンを食べるならば、その人は永遠に生きる。わたしが与えるパンとは、世を生かすためのわたしの肉のことである。」
それで、ユダヤ人たちは、「どうしてこの人は自分の肉を我々に食べさせることができるのか」と、互いに激しく議論し始めた。イエスは言われた。「はっきり言っておく。人の子の肉を食べ、その血を飲まなければ、あなたたちの内に命はない。わたしの肉を食べ、わたしの血を飲む者は、永遠の命を得、わたしはその人を終わりの日に復活させる。わたしの肉はまことの食べ物、わたしの血はまことの飲み物だからである。わたしの肉を食べ、わたしの血を飲む者は、いつもわたしの内におり、わたしもまたいつもその人の内にいる。生きておられる父がわたしをお遣わしになり、またわたしが父によって生きるように、わたしを食べる者もわたしによって生きる。これは天から降って来たパンである。先祖が食べたのに死んでしまったようなものとは違う。このパンを食べる者は永遠に生きる。」
宗派によってやや異なるようですが、概ね、<最後の晩餐>に由来すると言われる「聖餐式」において聖職者がパンと赤ワインを「聖別(聖なるものとする行為)」することで、それが「イエス・キリストの肉と血」へと変化して「聖体(聖なるもの)」となり、礼拝に参加している信徒に与えるとされています。打樋啓史(関西学院大学)『パンとワインが意味するもの』は、<最後の晩餐>はユダヤ教の共食儀礼にもとづいていると指摘しています。
まず食事の初めに家長がパンを取り、それを祝福し列席者全員に裂き与える。そして食事の終わりに、家長がワインの入った杯を取り、祝福の祈りを唱え、列席者に分け与えたのである。最後の晩餐におけるイエスの行為は、このパターンに合致している。
(打樋啓史、パンとワインが意味するもの、2013年)
このように<最後の晩餐>のテーブル上に描かれた食物の中には、ほぼ間違いなく「パン」と「ワイン」があるはずです。確かに、レオナルド・ダ・ビンチの名作<最後の晩餐>、ミラノのサンタ・マリア・デレ・グラツィエ聖堂の壁画の中央に座るイエスの左手の先にはパンらしい丸いものがあり、右手はワインを入れたグラスを持っているように見えます。しかし、問題はこの晩餐の主菜(メインディッシュ)が何かということです。イエスの前にある大皿には何も載っておらず(?)、左から3人目のアンデレ(両手を胸のあたりに上げて驚きのポーズをしている)と4人目のイスカリオテのユダ(右手に何かの袋のようなものを握っている/裏切ったと言われている)の間にある大皿(A)、右から3人目のマタイ(右端の3人が互いに顔を見合わせている)と4人目のフィリポ(両手を胸にあてて訴えかけるような動作をしている)の間の大皿(B)にも何かが描かれています。
福音書によれば、これはユダヤの過越祭(ペサハ)の最中の出来事であり、最後の晩餐は過越の食事(セデル)で会った。イスラエルのエジプト脱出を記念して祝われたこの祭りの日には、各家族がいけにえの子羊をエルサレム神殿で捧げ、儀式的な食事でそれを食することになっていた。イエスが弟子たちと共に行った晩餐も、このように供えられた子羊の肉を主菜とする会食で会ったと考えられる。
(打樋啓史、パンとワインが意味するもの、2013年)
しかし、宮下規久朗『食べる西洋美術史』(光文社新書)では、主菜が子羊の肉ではない可能性があると指摘しています。
(修復)以前はパンとワインの入ったコップ以外はほとんど見えず、過去に作られたこの絵の模写でも肉料理であったり魚料理であったりしたのだが、画面左には、魚がいくつも盛られた大皿(A)があり、テーブルのあちこちに、魚の切り身にオレンジかレモンの薄切りが添えられた取り皿が置かれているのが見えるようになった。 初期キリスト教時代からビザンチンにいたる最後の図像を見ると、子羊とおぼしき骨付き肉の大皿がテーブルの中央に置かれていることもあるが、魚が置かれているものの方が多い。古代カタコンベの壁画は、「最後の晩餐」ばかりではなく、「愛餐図」や「天上の食事」であることが多いが、ほとんどの場合には魚の大皿が登場する。
(宮下規久朗、食べる西洋美術史、光文社新書、2007年)
その典型的な図像が6世紀初めのサンタポリナーレ・ヌオーヴォ聖堂のモザイク壁画であり、確かに中央の大皿には2匹の大きな魚が描かれています。イエス・キリストが生まれ育ったナザレは、イスラエル北部にあるガリラヤ湖まで20キロほどのところにあり、「パンと魚の奇跡」(ルカによる福音書9章10〜17節)や「ペテロの魚」(マタイによる福音書17章24〜27節)をはじめとして新約聖書には魚にまつわる記述がいくつもあります。そもそもキリストの十二使徒のうち7人(聖書で確認できるのは、ペテロ、アンデレ、ヤコブ、ヨハネの4人)が漁師であったと言われています。また、禁教時代のキリスト教徒が、ギリシャ語でΙΗΣΟΥΣイエス ΧΡΙΣΤΟΣキリスト ΘΕΟΥ神の ΥΙΟΣ子 ΣΩΤΗΡ 救世主 の頭文字を並べたものが魚(イクテュスΙΧΘΥΣ 図)となることから、このマークが「イエス・キリスト」を示す暗号となっていたとも指摘されています。
「食べる」という行為が人にとって切実で、具体的なものであることから、「何をどのように食べるのか」ということが極めて重要な問題となります。その意味では、実際に何を食べたのかということよりも、何を食べていると思う(描く)のかの方がさらに重要であるとも言えます。<最後の晩餐>が実際に、どのように行われたのかはわかりません。しかし、キリスト教徒にとって「聖なる食物である『体』を共に食べるところに、共同体という『体』が成立するという…強烈な身体的・感覚的リアリティを持つ体験であった」ことは確かであり、「それゆえに、聖なる食物にどのような意味を付与し、どのような方法でそれを食べるかは、それを共食する共同体がいかなる集団として成立するかという問題と密接に関わって」いる(打樋啓史)のでしょう。