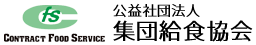vol.8
狩られるヒトの時代 〜「食べる」という行為の意味⑤
人類が、その脳を大きくするためには、他の動物たちを「狩る」ことで栄養豊富な肉類を手に入れる必要がありました。その意味では、私たちホモ・サピエンスの親戚であり、隣人でもあったネアンデルタール人がおそらく人類最高の「狩りの達人」であったと思われます。個体としての身体能力はもちろんのこと、集団で狩りをしており、脳容量も私たちより大きかったことがわかっています。クロアチアのヴィンディア洞窟で発見された2万9000年前のネアンデルタール人の骨に含まれる窒素の安定同位体を調べたところ、キツネやオオカミのような北方食肉類とよく似ており、タンパク質のほぼすべてを動物性食物からとっていた可能性が高いと考えられています(M.リチャーズ)。この優秀な狩人であるネアンデルタール人が、数千年間の現代人との共存期間を経て2万8000年ほど前に、なぜ絶滅してしまったのかはいまだに大きな謎であると言えます。ヨーロッパや中東における共存期間の間に何が起こったのか、少なくとも「ネアンデルタールは文化的ではないという古い見方を研究者がとらなくなった」ことは確かです(K.ウォン)。最近の研究では、私たちホモ・サピエンスのDNAにネアンデルタール由来の遺伝子が存在しており、一定の混血を繰り返していたことが明らかになっています。一つの可能性として考えられているのは、ホモ・サピエンスに比べてネアンデルタールの言語能力がやや劣っていたため、複雑なコミュニケーションを必要とする大きな集団や組織を形成できなかったことが原因ではないかということです。複雑な集団や組織が社会性をより発達させ、それを複雑な言語が支えていることは明らかです。
「狩る人(Man the Hunter)」という表現は、肉食によって大きな脳を手に入れたヒトの進化を説明するとともに、いまも続くヒトによる残虐な殺戮を説明する手段としても使われてきました。D.ハート・R.W.サスマン『ヒトは食べられて進化した』(2007年)では、ヒトが長い間「狩られる」立場(Man the Hunted)にあったこと、それによって進化を促されてきたことが指摘されています。
小柄な生き物で、脳がさほど大きくないためたいした分析力はもたず、平らな地面の上にすっくと立って、何百万年もそんなふうに生きてきた…要するに二本足で歩くカモだった。肉のついた蹠行動物、二足歩行をする食べ物、剣歯ネコのご飯、ジャイアント・ハイエナのおかず、ワニの箸休めというような、捕食者にとって飾りっ気のない簡素な食事だった。一言でまとめると、初期人類とは捕食される種である。このようにとらえると、私たちの起源は、慎重に行動しなければならず、仲間に頼らなければならず、危険を伝え合わなければならず、そして複雑なサイクルの単なる歯車たる身分を感受しなければならない、そんな数ある種の一つに過ぎないことが見えてくる。
(D.ハート・R.W.サスマン、ヒトは食べられて進化した、2007年)
確かに人類進化の過程を考えるうえで、捕食者としてのヒトの姿は一面でしかなく、他の霊長類と同様に捕食者によって狩られる被食者としての姿(捕食圧)も視野に入れなければなりません。おそらく初期人類が、自然条件下で生息する現生霊長類と同じ割合で捕食の影響を受け、その捕食圧が社会をつくるもっとも重要な環境要因となってきたと考えてもおかしくはありません。「狩られるヒト」として捕食者たちから身を守るために、初期人類は次のような7つの戦略をとったと考えられます。
- ①25〜75個体からなる比較的大きな集団で暮らしていた。
- ②多彩な移動様式をもっていた。
- ③柔軟性のある社会組織をつくっていた。
- ④社会集団の中にまちがいなく男(オス)がいた。
- ⑤男を見張りとして使っていた。
- ⑥泊まり場を注意深く選んだ。
- ⑦賢くあれ、そして相手より一歩先んじること。
動物性食物を食べること(肉食)が植物性食物のみを食べること(菜食・穀食または草食)に比べて、生きるうえで有利であることはエネルギー効率の問題だけではないようです。高橋迪雄『ヒトはおかしな肉食動物』(2005年)の中で、以下のような指摘をしている。
三大栄養素のうち、炭水化物あるいは脂肪だけを食べて生きていくことはできませんが、タンパク質だけを食べて生きていくことは可能です(もちろんこの時、ビタミン、ミネラルなどの微量栄養素が満足された条件であることが前提ですが)。哺乳類の原型的な食性が肉食であることは、このことからも十分納得されます。
(高橋迪雄、ヒトはおかしな肉食動物、2005年)
人類が約1万年前に始めた農耕は、極めて効率よく食物を供給するシステムであったため人口の急増と社会組織の拡大をもたらしましたが、「穀物を栽培してその種子を食べる営み」は同時に「穀物に大きく依存した『草食』まがいの食生活を始めた」ことにもなります。穀物由来のタンパク質とヒトあるいは高等動物が必要とする必須アミノ酸の組成が大きく異なっているため、「草食化」がスムーズには進んだわけではなさそうです。例えば、コムギはリシンとメチオニンの含有量が極端に少なく、トウモロコシでは、トリプトファンとリシンの含有量が著しく低いため、「過食」や畜産のように何らかの方法で、これを補う必要がありました。
その意味で、ジャガイモのタンパク質の必須アミノ酸の組成バランスが、ヒトの要求するそれに極めて近いことが注目されます。まさにジャガイモは「貧民の肉」として、18〜19世紀の北ヨーロッパの低所得者層の用事死亡率を減少させ、激しい人口増加を引き起こしたと考えられています。このジャガイモへの過度な依存が、他方でアイルランドに「ジャガイモ飢饉」を引き起こし、多数の餓死者とアメリカ大陸への多くの移民を生み出したことも忘れてはなりません。