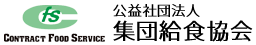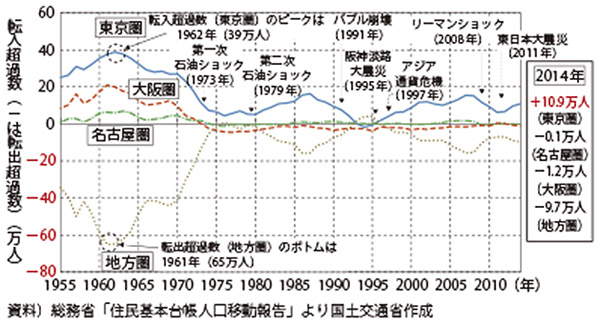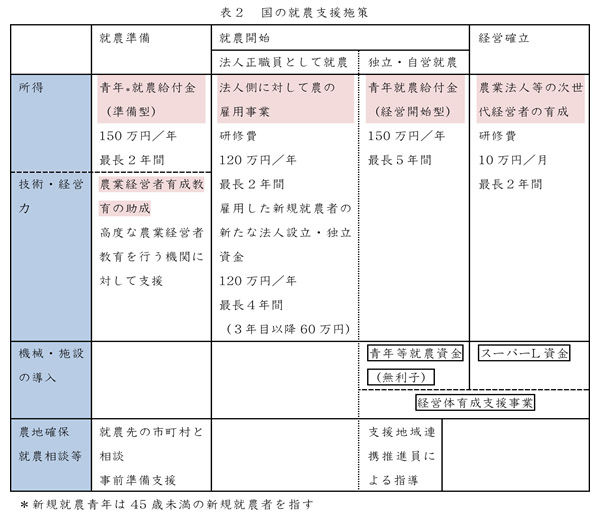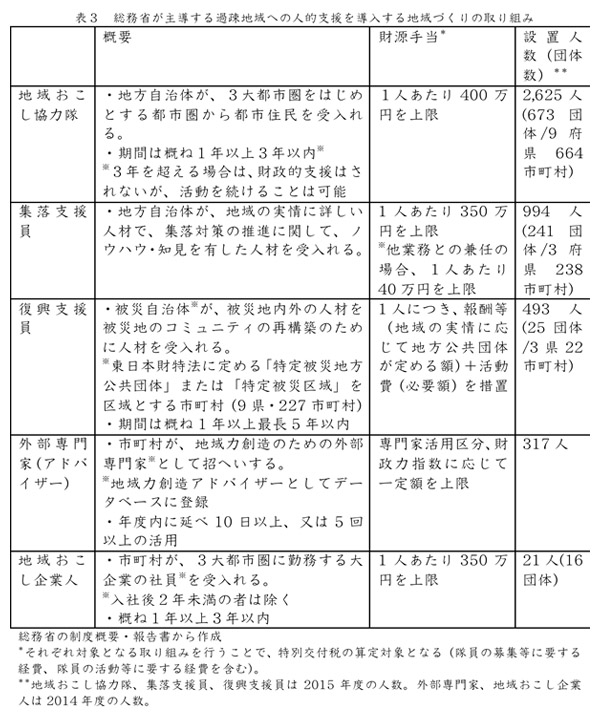vol.14
「おふくろの味」VSファストフード ~食育と地域づくり④
食育としての「おふくろの味」
家庭における食育を考えたとき、ある年齢以上の日本人にとって「おふくろの味」と呼ばれるものが独特の意味をもっています。「おふくろの味」を理解することは、現代の食をめぐる問題や、家庭における家族の関わり方の問題を解決する一つの可能性をもっています。「おふくろの味」には、3つの座標軸を設定することができます。①「食」に媒介される人と人との<関係性>の軸、②「食」の素材や調理法、味覚などがもつ<土着性>の軸、③「食」が示す<非市場性>の軸、です。
「食」に媒介される人と人との<関係性>の軸
<関係性>が低い状況とは、自分で食べているモノがどこから来たのかわからない、だれがどのようにつくっているのかわからない状況です。食における<関係性>とは、コミュニケーションといいかえることができます。「おふくろの味」には、母親(父親でも兄弟姉妹でも食堂のおじさん、おばさんでもよい)という明瞭な作り手が存在します。家庭やコミュニティにおける食は、具体的で身近な作り手との対話としての意味合いをもっており、そこに「安らぎ」や「安心感」などの精神的な充足感を感じることも多いのです。「おふくろの味」とは、身近な人(もしくは身近に感じる人)とのコミュニケーションという性質をもつものであるといえます。「食」の素材や調理法、味覚などがもつ<土着性>の軸
<土着性>は、「おふくろの味」がしばしば「ふるさとの味」と重なり合うことに起因します。私たちの食は、つい最近まで特別なハレの食事を除いて、自分が暮らす日常生活圏の周辺で素材が調達され、家や地域に伝わる方法で調理されてきました。生まれ育った風土によって、それぞれ異なる味覚が生まれ、それが「ふるさとの味」と呼ばれるものになります。これだけ食材が世界から供給され、調理法が画一化しているように見えても、味覚は概して保守的なものです。ファストフードやインスタント食品、スナック菓子ですら、国別の味覚だけでなく、地域ごとの味覚に配慮した製品をつくるのです。「食」が示す<非市場性>の軸
<非市場性>とは、お金に換算することができないということです。家族の食事をつくることは、労働の対価を求めるものではありません。外食産業や中食産業の発展によって、内食である家族の食事の一部が外部化(社会化)・市場化されてきました。ジェンダー・バイアスによって家庭内で食事を用意することが母親の役割のように思われてきましたが、「おやじの味」であっても構いません。若い夫婦やパートナーが共同生活する場合にも、しばしば交代で食事を用意することがあります。こうした食事を用意することは無報酬でなされるのであり、市場的な関係が持ち込まれないということでしょう。ファストフードが世界を席巻する
「おふくろの味」の対極をなすものが、ファストフードです。2007年6月末までは、確かにマクドナルド・ハンバーガーは世界一の店舗数(3万1677店)を誇っていました。これを抜いたのが、セブン・イレブン(3万2711店)です。『ファストフードが世界を食いつくす』(2001年)で知られるエリック・シュローサーは、ハンバーガーの歴史と特徴を簡潔に紹介しています(『おいしいハンバーガーのこわい話』、2007年)。 ハンバーガーのルーツに諸説はあるものの、19世紀の終わりにミートボールをつぶしてパンに挟んだ新しいサンドウィッチを「ハンバーガー」と呼んだものが起源のようです。その後、1948年にカリフォルニア州パサディナに開店したマクドナルド兄弟の店が、世界に広がるマクドナルド・ハンバーガーの始まりだそうです。この店には調理人とカウンターの受付係しかおらず、紙皿に紙コップ、ハンバーガーとチーズバーガーの2種類しかつくらない。車で移動することを前提に、「運転中に手で持って食べられる」商品を安価に提供する「スピーディーサービス・システム」を導入しました。レイ・クロックの経営手腕
この店に注目したのが、ミルクシェイクの撹拌機を売りにきたセールスマンのレイ・クロックです。彼は共同経営者となって、新しいタイプのフランチャイズ方式を導入しました。「その方式とは、地元の事業家が自分のカネでマクドナルドの店を新しくひらき、クロックが経営の仕方を一から十まで教える、そして店の利益は分け合う」というものでした。 その成功の鍵は「画一性(ひとつひとつの特別な事情を考えず、すべて同じにそろえること)」でした。「レイ・クロックは、新しいマクドナルドの店をどれもまったく同じにすることを求めた。看板も同じなら、建物も、メニューも同じでなくてはならない。そしてなによりも、食べものがまったく同じ味であること」を求めました。こうしてレイ・クロックはライバルとの競争に打ち勝ち、マクドナルド・ハンバーガーの店をアメリカ全土に、そして世界中に広げたのです。このレイ・クロックの凄腕と人物像については、映画『ファウンダー ハンバーガー帝国のヒミツ』(2017年)をご覧ください。「近代ハンバーガー革命史AD1971〜1990」
日本にハンバーガーがどのように広まったのか、それをパロディとして見せてくれるのが『カノッサの屈辱』(1991年)です。「近代ハンバーガー革命史AD1971〜1990」の序文は「我が国のハンバーガーは、マクドナルド王朝の権力下のもと、産声を上げた。王朝の模倣から始め、やがて打倒マクドナルドの悲願を抱き、王朝独裁に立ち向かっていった、勇気あるハンバーガー諸党の戦いの歴史である」と始まります。マクドナルドの1号店が開店した1971年は「銀座1号店にてマクド=カルタ発布 従業員に完璧な接客態度を要求する」と解説されます。1970〜80年代の日本の風俗を知る歴史好きにはたまらない書き方であり、日本のハンバーガー史をこれほど面白く、わかりやすく解説しているものはなかなかありません。ここまでハンバーガーが人気を集めたヒミツは、その独特の「おいしさ」「手軽さ」とともに値段の「安さ」があるのではないでしょうか。その後、1995年頃から低価格戦略をとったハンバーガー業界は、一時期、ハンバーガー1個を65〜80円で販売したこともあります。なぜ、これほどまでにハンバーガーを安く売ることができるのかを解説した本が、『〔儲け〕のカラクリ』(2002年)です。利益率5%で100円のハンバーガーをいくら売っても儲からず、ドリンクやポテトとのセット販売で利益を上げていたのです。
スーパーサイズ・ミー
ハンバーガーを1ヶ月間、三食食べ続けると、私たちの身体はどのようになってしまうのでしょうか。それを監督自らが実験したのが、モーガン・スパーロック監督の映画『スーパーサイズ・ミー』(2004年)です。彼は4つのルールに基づいて30日間の実験を始めました。①マクドナルドのメニューしか食べてはいけない(水も含む)。②勧められたら必ず「スーパーサイズ」にする。③すべてのメニューを制覇する。④朝・昼・晩の3食欠かさず食べる。 その結果、実験前と30日後のスパーロック氏の身体は、身長188cm→同じ、体重84・3kg→95・3kg(11kg増)、体脂肪率11%→18%(7%増)、総コレステロール値168→233(65ポイント増)となりました。実際には、毎日3食をマクドナルドで食べる人は(まず)いないでしょうから、極端な実験であることは確かです。しかし、高カロリー・高タンパクのファストフードを食べ続けると身体がどのようになってしまうのかを知り、世界中に展開するファストフード業界の実態を学ぶにはよい教材だといえます。 さて、「おふくろの味」とファストフードの間に生きる私たちは、どこに食育の可能性を見出せばよいのでしょうか。朝岡幸彦(あさおか ゆきひこ / 白梅学園大学特任教授/元東京農工大学教授)