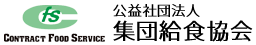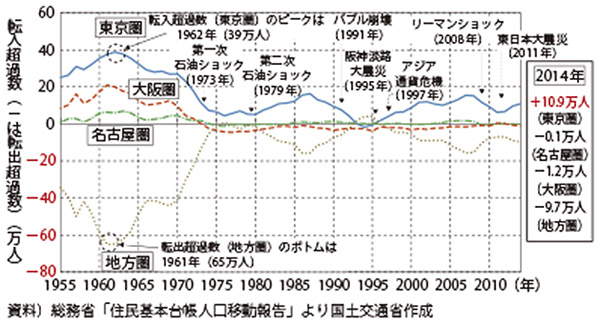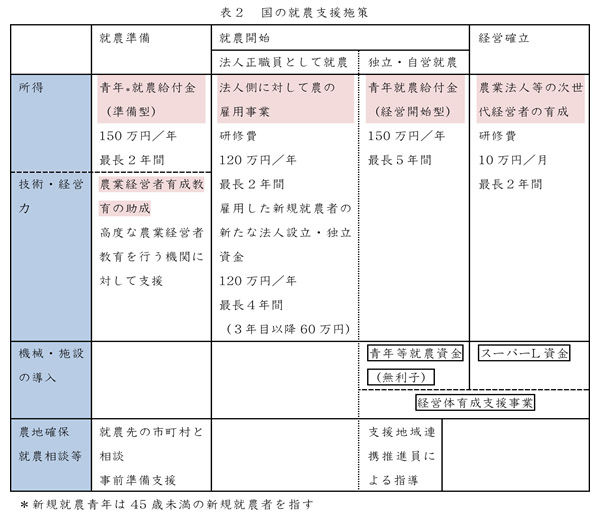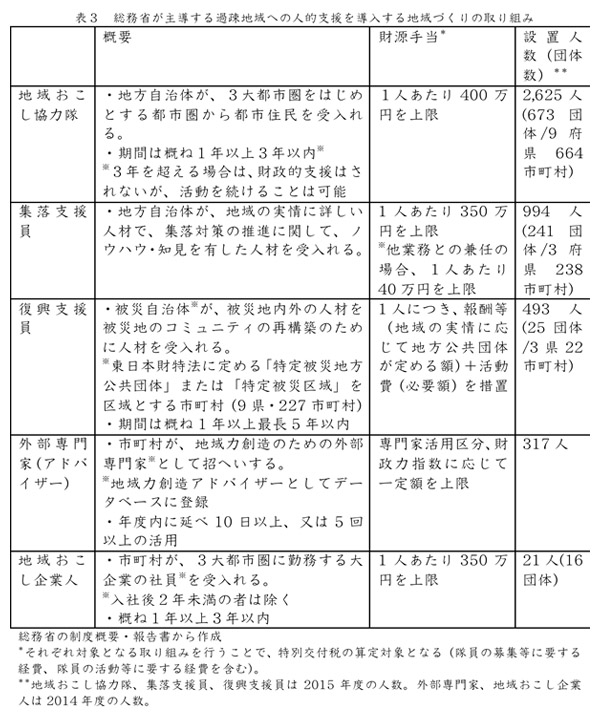vol.16
火の賜物 ~食と食育を考える100冊の本(1)
リチャード・ランガム『火の賜物 ヒトは料理で進化した』NTT出版、2010年
ここで少し視点を変えて、食や食育について様々な論点から述べている本を、(断続的になるかもしれませんが)しばらく紹介してみましょう。生のものだけ食べ続けると「死んでしまう」!?
ここでご紹介するリチャード・ランガムは、人間が「野生のものを生で食べて長期間生きたという記録はどこにも見当たらない」「動物を生で食べて生き延びた最長のケースでもわずか数週間である」と断言しています。彼が認める生のものだけ食べ続けて生きた最長の記録は、1972年にドゥーガル・ロバートソンとその家族が太平洋でシャチに船を破壊され、救命ボートに38日間閉じこめられた記録です。「生で食べない」ために、私たちが「料理」していることが重要だというのです。ここでいう「料理」とは、加熱を中心にさまざまな形で人(ヒト)が食物を消化・吸収しやすいように手を加えて加工する行為だと考えられます。もちろん、人が加工しなくても食物が変性する可能性はあるのですが、その場合の有用な変性は偶発的で頻度が少ないため、ヒトの身体そのものを変化させる可能性が少ないといえます。つまり、私たち(ヒト)は、ある時期から食物を「料理」することを前提に進化してきた結果として、料理しない「生」のものを食べ続けると死んでしまうと考えるわけです。
しかし、著者が槍玉に上げる「生食主義者」と呼ばれる人たちのように、現代社会には「手に入るかぎり100パーセントか、それに近い割合の食物を生で食べる人々」がいることも確かです。彼らは、なぜ生きていられるのでしょうか。これはベジタリアン(菜食主義者)の話ではありません。ベジタリアンは料理を否定しているのではなく、肉食を拒否しているのですから著者にとっては批判の対象となりません。
ギーセンの調査の参加者たちがスーパーマーケットで買ったものを食べていたことを忘れてはならない。それらは現代農業の典型的な作品ーできるだけ美味しくなるよう栽培された果実、種、野菜ーである。〝美味しい〟とは、エネルギーが豊富ということだ。人が好むのは、消化不能の繊維が少なく、水溶性の炭水化物が多い、たとえば砂糖のような食物だからだ。農業の発達によって、リンゴ、バナナ、イチゴといったスーパーマーケットで買える果実は、それぞれの野生の祖先よりはるかに高品質になっている。(p.24)
農業が発達するまで、たとえ料理したものを食べていても、定期的な飢餓─一般的には年に数週間ーに悩まされるのは人類の宿命だった。(p.25)
「料理」がヒトを進化させたー「料理」の始まり
W・R・レナード『美食が人類を進化させた』(2003年)を紹介した「vol.7 美食がヒトを進化させた ~「食べる」という行為の意味④」では、「肉食」がヒトの脳を巨大化させたと指摘しました。しかし、ことはそう単純ではなく、「料理」の発明という行為こそがヒトの進化を大きく進めたと主張しているのが、本書の特徴です。ここで再び、脳容積の一般的な発達傾向を見てみましょう。400万年前の初期①アウストラロピテクスが400cc(チンパンジーと同じ)、200万年前の②アウストラロピテクス・ボイセイ(頑丈型)が500cc、同じ頃の③ホモ・ハビリス(華奢型)が600cc、170万年前の④ホモ・エレクトスが900cc、20万年ほど前に⑤ホモ・サピエンスが1,150cc、⑥現代人(ホモ・サピエンス)が1,350ccとなっています。ここで注目されているのが、③→④ホモ・ハビリス(200万年前)からホモ・エレクトス(170万年前)への脳容量の増大と、④→⑥ホモ・エレクトスからホモ・サピエンス(現代)への脳容量の増大です。レナードは、この③→④の変化を「肉食」の開始で説明しようとしたわけです。
しかし、ランガム(著者)は脳容量の増大を一連の過程として説明しようとしています。
このように葉から根への移行、肉食への移行、そして肉や加工という食事の変化で、600万年前のチンパンジーに似た祖先から、200万年前のハビリスに至るまでの脳の成長を説明することができる。その後の脳容量の拡大はこれより連続的だ。(p.119)
まず、最初のヒトが他の類人猿との共通の祖先から分かれた500万年から700万年前に、森から川や湖の畔(水辺)に棲家を移して、「食べるものを葉からより高品質の根に移した」ことに注目します。アウストラロピテクスの食糧源として重要な場所は、スゲやスイレンやガマがよく育ち、今日の狩猟採集民にとっても澱粉質の食物の〝スーパーマーケット〟になっている、川や湖の畔だった。(p.116)
ついで、①→③の変化を「肉食」の開始によって説明し、問題の③→④の変化は「料理」の発明と考えているのです。次の顕著な増加期において、脳容量はアウストラロピテクスの約450立方センチメートルから、ハビリスの612立方センチメートルへと30パーセント以上増加した。アウストラロピテクスとハビリスの体重はほぼ同じだから、相対的な脳の増加はかなり大きい。考古学の証拠によれば、この時期の食事上の大きな変化は、肉食が増えたことだ。つまり、肉が脳の成長を可能にしたのだろう。脳がこれほど大きくなったということは、ハビリスは肉に手を加えて食べていたとも考えられる。類人猿やヒトの歯は容易に肉を切り裂くことができず、口も比較的小さい点で不利だ。…胃も生肉の塊を効率よく消化することができない。(p.117)
そして、最後の④→⑥の変化は「料理の手法」が次第に改善され続けた結果と考えているようです。それは、「食物を火の上に置く」→「酸化鉄の使用、骨からの道具作成、長距離の交易など」の文明的な行動→「地面を掘って作るオーブンの初期形態」→「容器を使った料理」という過程を経たとしています。
料理は発明後長い時間がだったあとも脳の進化に影響を与えつづけたはずである。手法が改善されるからだ。おそらく初期の手法はもっぱら食物を火の上に置くことだっただろう。(p.121)
大きな飛躍のあいだに起きた安定的な脳容量の拡大は、料理の手法が次々と改善されていたからと考えれば、容易に説明がつく。ホモ・ハイデルベルゲンシスが登場したときの顕著な拡大は、おそらく重要な料理法の進歩がいくつかあったせいだろう。(p.122)
約20万年前、現在の私たちの種であるホモ・サピエンスにも同じことが起きた可能性がある。…この移行とほぼ同時期に、酸化鉄の使用、骨からの道具作成、長距離の交易など、初めて文明的な行動が見られるようになった。料理の手法にも似たような文明化があったかもしれない。(p.123)
地面を掘って作るオーブンの初期形態は、発明として影響力が大きかった可能性がある。(p.123)
同様に、容器の使用も料理の効率を高めたにちがいない。やはりこれも消化の労力を減らし、脳の拡大に貢献したのではないだろうか。陶器は1万年ほどまえの発明だが、そのはるかまえから、自然に存在するものが料理用の容器として使われていた可能性がある。(p.124)
そういった技術から、容器を使った料理へのステップはほんのわずかだ。初期のホモ・サピエンスが自然の容器でものを熱した痕跡は約12万年前にさかのぼる。…残念ながら、初期のヒトが工夫を凝らして植物を使っていた料理法の多くはなんら痕跡を残さず、私たちの知りえないものとなった。(p.124-125)
このように料理法の発達は200万年の人類の進化において、類を見ない継続的な脳の拡大に貢献した。(p.126)
残る唯一の選択肢は、ハビリスからホモ・エレクトスに移行したもっとも古い変化である。これは190万年から180万年前に起こり、後世の移行よりもはるかに大きな解剖学的変化をともなった。…三つの代表的な臼歯の表面積は、ハビリスから初期のホモ・エレクトスにかけて21パーセント減少した。ハビリスの大きな臼歯は、何度も噛まなければならないものを大量に食べていたことを物語っている。(p.98-99)
「料理」がヒトの身体を形づくる
ヒトの身体的な特徴の一つは、もっとも近いチンパンジーなどの霊長類に比べて、「消化に関するさまざまな部位がすべて小さい」ということです。脳という高エネルギー組織を大きくするためには、より多くのエネルギーを食物から取ることとともに、身体の他の部分のエネルギー消費を減らす必要があります。料理に適応することの進化的な利点は、ヒトの消化器官をチンパンジーなどの類人猿と比べれば明らかだ。いちばんのちがいは、消化に関するさまざまな部位がすべて小さいことである。口、顎、歯、胃、大腸、小腸ーすべてが小さい。かつてこれらの部位の異常な小ささは、たいてい肉食の進化的帰結と考えられてきた。が、ヒトの消化器官の設計は、生肉を食べることより、料理したものを食べることに適応したという説明のほうが合理的だ。(p.43)
とりわけ、外見上目立つのが口の小ささです。見た目(開口部)が小さいだけでなく、体重がヒトの2/3に過ぎないチンパンジーと容積は同じくらいしかありません。さらに顎の筋肉(噛む力)が極めて弱いのです。ヒト以外の類人猿にある矢状稜と呼ばれる頭蓋骨の頂点にある骨がない(退化した)ために、咀嚼する筋肉(側頭筋と咬筋)がほぼ半分になっています。いつからこの非力な顎になったのかはほぼわかっており、約250万年前に私たちの祖先にMYH16という(顎を退化させる)遺伝子が広がったとされています。さらに、人の胃の表面積は同じ体重の典型的な哺乳類の1/3以下、大腸も同じ体重の類人猿の60%以下に過ぎません。小腸だけが、他の霊長類よりやや小さめであるのは、体重を考慮した基礎代謝率が同じであるからと考えられています。こうした事実から明らかなことは、「ヒト(の消化器)はこれまで調べられたどの霊長類より小さい」ということであり、消化器の重さが同じ大きさの霊長類の60%しかないということです。こうしてヒトの消化器が小さくなったことで毎日のエネルギー消費が約10%少なくなり、その分を高エネルギー消費器官である脳に回すことができるということです。ここまでは肉食説によっても説明できるのですが、これでは消化能力の低いヒトがなぜ効率的に食用の植物を消化できるのかが説明できないのです。
ヒトは炭水化物(植物から得られる)か脂肪(少数の動物から得られる)のどちらかを大量に必要とするので、植物は生命維持に不可欠の食物だ。炭水化物も脂肪もなければ、エネルギー摂取をタンパク質に頼らなければならない。過度のタンパク質摂取は中毒症状を引き起こす。タンパク質中毒の症状には、有毒レベルの血中アンモニア、肝臓や腎臓の機能障害、脱水症状、食欲不振などがあり、究極的には死に至る。(p.50)
ヒトにとって安全なタンパク質摂取の上限は、全カロリーの50パーセント前後なので、残りのカロリーはクジラの脂のような脂肪か、果実や草の根のような炭水化物から得なければならない。(p.51)
たとえば、複素環アミンやアクリルアミドに代表されるメイラード化合物を見てみよう。…料理説によれば、ヒトはメイラード化合物にさらされた長い進化の歴史のなかで、ほかの哺乳類より、その有害性に対する抵抗力を身につけてきた。これは重要な問題だ。加工した多くの食物に含まれるメイラード化合物は、ほかの動物にはガンを引き起こすことで知られる。…2002年、ポテトチップスなど、広く販売されているジャガイモ食品にアクリルアミドが発生していることがわかった。これがほかの動物と同じように発ガン性を持つとなると危険である。一方、発ガン性を持たないなら、それはヒトがメイラード化合物に適応していること、熱を加えた食物に長くさらされていることの証左と言えるかもしれない。(p.53)
同様に、ほかの類人猿より毒素に抵抗力がないことも、ヒトが料理に適応したからかもしれない。霊長類が食べる多くの食物を試しに食べてみた私の経験では、野生のチンパンジーが食べるものはほかのサルが食べるものより美味しい。それでもチンパンジーが選ぶ果実、種、葉のなかには、あまりにも不味くて呑みこめないようなものもある。それらの味は強烈であり、栄養以外の含有物があることを如実に示している。その多くはヒトにとって有毒だろうが、チンパンジーにとってははるかに害が少ないはずだ。(p.54)