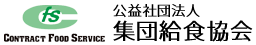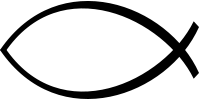vol.4
生きるために「食べる」 ~「食べる」という行為の意味①
これまで、(1)アンパンマンはなぜ自分の顔を食べさせなければならないのか、(2)ドラえもんはロボットなのになぜどら焼きを食べるのか、(3)「最後の晩餐」にはなぜ特定の食べ物が描かれなければならないのか、について考えてきました。それを一言でいえば、それぞれの主人公がそれぞれの場面で「実際に何を食べるのか」ということよりも、「何を食べることが期待されているのか」ということの方が大切だと考えられているからです。もっと簡単にいえば、イメージが大切なのです。人は見かけでいろいろなことを判断しがちです。同じように、「食べる」という行為も、そのキャラクターの性格を決める大事な要素なのです。
さて、
人(ヒト)はなぜ「食べる」のでしょうか?
それは、食べないと死んでしまうからです。なぜ、食べないと死んでしまうのでしょうか?
こんな当たり前とも思えることに、とても重要な“問い”が含まれているのです。つまり、私たちヒトを含む「生物(生き物)」とは何かという定義に関わる問題です。福岡伸一は『生物と無生物のあいだ』(講談社現代新書、2007年)という本の中で、生命(生物)を「動的平衡(dynamic equilibrium)にある流れ」と定義しています。
彼が注目するのは、ルドルフ・シェーンハイマーが1930年代後半に行った一つの実験です。それは窒素の同位体(アイソトープ)である重窒素を、「追跡子(トレーサー)」にするという画期的なアイディアに基づくものです。実験用ネズミにある一定の短い時間だけ、重窒素で識別されたロイシンというアミノ酸を含む餌を与えたのです。餌は生命維持のためのエネルギー源となって体内で燃やされるので、摂取した重窒素アミノ酸もすぐに燃えてすべて尿として放出されるはずです。
しかし、実験結果は彼の予想を鮮やかに裏切っていた。…与えられた重窒素のうち何と半分以上の56.5%が、身体を構成するタンパク質の中に取り込まれていた。しかも、その取り込み場所を探ると、身体のありとあらゆる部位に分散されていたのである。…つまり、ネズミを構成していた身体のタンパク質は、たった3日間のうちに、食事由来のアミノ酸によってがらりと置き換えられたということである。
(福岡伸一、生物と無生物のあいだ、講談社現代新書、2007年)
ここに、「私たちは、なぜ食べないと死んでしまうのか」という問いへの明確な一つの答えが与えられています。それは、私たちの身体のすべてが食べたもので置き換わっているからです。皮膚や爪や毛髪という再生を実感できる表層だけでなく、血液や臓器や骨や歯ばかりでもなく、再生しないと思われている心臓や脳を含む、身体のあらゆる部位で例外なく「絶え間ない分解と合成が繰り返されている」のです。私たち人の身体がどれくらいの期間に「食べたもの」で置き換わってしまうのかはわかりませんが、少なくとも何年かぶりに会った知り合いは以前とは違った分子で構成されている別物ということになります。
つまり、「食べないと死んでしまう」ということの意味は、食べなければ身体を構成する分子がなくなり、文字どおり「(千の風になって)消えてしまう」のだと考えられるのです。
肉体というものについて、私たちは自らの感覚として外界と隔てられた個体としての実体があるように感じている。しかし、分子レベルではその実感はまったく担保されていない。私たち生命体は、たまたまそこに密度が高まっている分子のゆるい、「淀み」でしかない。しかも、それは高速で入れ替わっている。この流れ自体が、「生きている」ということであり、常に分子を外部から与えないと、出て行く分子との収支が合わなくなる。
(福岡伸一、生物と無生物のあいだ、講談社現代新書、2007年)
私たち生物の身体を分子レベルでみると、それは容器(分子の入れ物)ですらなく、分子の流れの「淀み」だったのです。絶えず新しい分子を供給し続けなければ、私たちの(生命)活動が停止してしまうだけでなく、身体そのものが完全に失われてしまうのです。これは、シュレーディンガーが予言した「エントロピーの増大に抗って秩序を維持する」という生命のイメージ(1944年)を、身体というシステムの耐久性と構造を強化するという方向ではなく、むしろ「そのしくみ自体を流れの中に置く」という新たな方向を示しています。私たちの身体の構造を生み出しているDNAも、私たちが食べたもので作られている、という言い方もできるでしょう。
さて、死んだ後の身体の崩壊をリアルに描いた絵の代表が、「九相図(くそうず)」と呼ばれるものです。例えば、「九相詩絵巻」は、次のような段階を経て描かれています。
- 序 生前の相(すがた)
- 第一 新死の相
- 第二 膨張(ぼうちょう)の相
- 第三 血塗(けっと)の相
- 第四 肪乱(ほうらん)の相
- 第五 青瘀(せいお)の相
- 第六 噉食(たんじき)の相
- 第七 骨連(こつれん)の相
- 第八 骨散(こつさん)の相
- 第九 古墳の相
(小松茂美編、コンパクト版日本の絵巻7 餓鬼草紙 地獄草紙 病草子
九相詩絵巻、中央公論社、1994年)
ほとんどの人は、人を含む死んだ生物の身体の変化をじっくり観察する機会はないのですが、死とともに生物の身体は次第に崩壊し、分解されて、最後は土に還ると信じられています。逆に、土から生まれた分子で私たちは構成されており、その分子を「食べる」ことで身体に取り込んで身体を維持していると言えるかもしれません。また、人の寿命が延びて高齢化する中で、「老衰死」と診断されるケースが増えつつあります。これは、加齢によって身体を形成する細胞や組織の能力が低下して、多臓器不全による恒常性(ホメオスタシス)・生命活動の維持ができなくなることによる死であるとされています。「食べる」能力が失われるということは、「老衰」の直接の原因であると考えられます。
ところで、「シンギュラリティ(技術的特異点)」という概念を提唱しているレイ・カーツワイルは、そのもっとも重要な要素を「指数関数的成長の力(power of exponential growth)」であると述べ、次のような予言をしています。
それほど遠い将来のことではなくて、おそらくあと12年もしないうちに、われわれは毎年1年あまり寿命を延ばしていくことになるでしょう。ここが分岐点になると思います。「長寿脱出原理(longevity escape philosophy)」と呼んでいますが、バイオテクノロジーの加速度的な発達によって、寿命を1年延ばすために必要な研究期間が、1年よりも短くなっていきます。
(吉成真由美・インタビュー編、人類の未来、NHK出版社、2017年)
そう、私たちは間もなく「死なない」社会を迎えるかもしれないのです。「それはいくら何でもありえないでしょう」と思われるかもしれませんが、首相官邸で開かれた第1回人生100年時代構想会議(2017年9月11日)でリンダ・グラットン議員(ロンドンビジネススクール・マネジメント実践・教授)は、「2007年生まれの子どもの50%が到達すると期待される年齢」として日本人は107歳である(10歳の子どもの半分が107歳まで生きる)と報告しているのです。さて、私たちは、どのように「食べて」、どのように生きればよいのでしょうか。