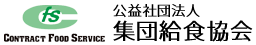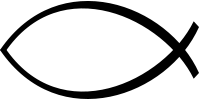vol.5
口という器官の不思議な進化 ~「食べる」という行為の意味②
「食べる」ことで、人は生き続けることができます。食べなければ、私たちの身体を構成する材料が得られない、身体がなくなってしまうのです。その入り口となる器官を、「口(クチ)」と呼びます。すべての生物に口があるかというと、実はそうとも言えません。例えば、植物は光合成によってエネルギーを生みだし、キノコなどの菌類は菌糸という細胞によって他の生物の遺骸を分解して「食べて」います。とはいえ、私たちにとって「口」がかけがえのない「食べる」ための器官であることは間違いありません。馬場悠男さんは、次のように定義しています
陸上動物の祖先がまだ海中で暮らしていた時代、おそらく5億年以上前のあるとき、海中を一定方向に動く動物の前端に孔(アナ)が開き、そこから栄養物を体内に取り込むようになった。あるいは、栄養物を体内に取り込む孔を常に前にして、海中を一定方向に動く動物が現れたということかもしれません。この前端に開いた孔こそが、のちに「口」と名づけられることになる器官にほかなりません」
(馬場悠男、「顔」ってなんだろう?、NHK出版社、2009年)
これは口の起源であるとともに、「顔」の始まりでもあります。馬場さんは、口を中心として「一定方向にある程度の速さで動く動物にのみ<顔>ができる」と指摘します。口ができると、①より早く、より確実に食物を取り込む、②生存していくために外敵や障害物をいち早く察知しようとして、口の周辺に目・鼻・耳等の感覚器官が集中するようになり、「体の前端・口・感覚器官という三点セットが揃ったとき、『顔』というものが形成された」と述べています。
人間を含む大部分の脊椎動物や昆虫の体は左右対称にできているので、前と後ろ、左と右の概念が生まれ…そのため、方向も一定にできるし、前端も決まる。
(馬場悠男、前出、2009年)
ウニやヒトデのような動物には、口はありますが顔がありません。それは、ウニやヒトデには先端も方向もないからなのですが、顔があるからといって私たちがイメージする口と同じであるとは限りません。無顎類と呼ばれるヤツメウナギには、口も前端も感覚器官の集中もあるので、顔が存在します。その口には顎(アゴ)がないため、ただの孔が先端に開いているだけで、閉じることはもちろん嚙み砕くこともできません。
顎のないヤツメウナギには口のすぐ後ろ、頭の後方に8つもの鰓(エラ)が並んでいます。いうまでもなく、ヤツメウナギの「目」と思われていたものは水の中で呼吸するための「鰓」でした。
古い魚たちが顎を作る材料に選んだのは、なんとこの鰓の一部だと考えられている
(遠藤秀紀、人体 失敗の進化史、光文社新書、2006年)
遠藤秀紀さんによると、この鰓の構造がいかに下顎に適した位置と形になっているのかは、食卓に上がった焼かれたサンマの姿をよく観察するとわかるらしい。サンマは口から取り入れた水を鰓に通すことで酸素を吸収するため、鰓は血管をたくさん通した柔らかい組織となっています。その柔らかい組織を支える骨格を鰓弓(サイキュウ)と呼び、目の少し後方で少し下(腹)側にあります。鰓弓は下顎のすぐ後方の位置にあり、しかもかなり似た形をしています。
ここで、脊椎動物に頭が無かった時代を思い浮かべてみよう。口の孔は開いているが、そこに開閉する顎構造は存在しない。口の周囲を見れば、そこには顎よりもはるか昔から存在する鰓弓(鰓)が陣取っている。鰓弓は効率よく水から酸素を得られるように、左右に何枚も同じ構造を作り上げている。もしこの鰓弓の前方部分、つまり口に近い部分に蝶番が生じて、しかも筋肉で意のままに開閉できるようになったとしたら…まずはその動物は、口の孔の周囲に、開け閉めできる扉を持つことになるのではないか。観音開きを左右ならぬ上下にしたような便利な扉が口の上下に備わることになる。顎構造の上半分は、もともとあった頭の骨と一体になり、上顎が出来上がる。専門用語では、口蓋方形骨(コウガイホウケイコツ)などと呼ばれる、頭の一部となっている構造だ。一方、下半分は、鰓弓のパーツを使いながら、下顎へと発展していけばよい。
(遠藤秀紀、前掲書、2006年)
なんと開きっぱなしだったヤツメウナギの口は、鰓の蝶番を転用することでパクパク開け閉めできる魚や私たちのような口になったと考えられているのです。確かに、ただ開いているだけの孔では、せっかく口に入ったエサも簡単に逃げてしまうことができますし、逃げられないためには掃除機のように強力に吸い続けるか、必死に前進してエサを消化管まで送り込まなければならないですね。口に蝶番が付きさえすれば、エサに逃げられることもなく、じっくり消化管まで送り込むことができます。
ところが、せっかく手に入れた蝶番付きの口を手放さなければならない危機を迎えます。海から陸上に私たちのご先祖様が進出する時に、大きな問題に直面するのです。同じ哺乳類の仲間であるイルカやクジラの耳には耳輪(ジリン)や耳垂(ジスイ/耳たぶ)などによって構成される耳介(ジカイ)または耳殻(ジカク)と呼ばれる部分が見当たりません。魚にも耳介がないのですが、イルカやクジラはおそらくもともとあったものが退化してしまったのかもしれません。なぜ退化したかというと、耳介の大切な役割である集音機能が水中ではあまり必要ないからなのです。プールに耳栓をせずに水中に潜ると、周りの音がすごくよく聞こえるという経験をしたことはないでしょうか。水の中は空気中に比べて音の伝導率が高いのです。
つまり、海から陸上に進出した私たちのご先祖様は、鰓呼吸から肺呼吸へという呼吸方法の転換とともに、「音が聞こえない!」、音をなんらかの方法で増幅することを求められたのです。その結果として、最初は爬虫類のように地面近くに頭を配置し、大地の振動を顎の骨(骨伝導)で拾っていたようですが、次第に頭の位置を高くした哺乳類には、その手が使えません。そこで思い切って、せっかく魚時代に手に入れた顎の蝶番を耳の奥にしまいこんで、耳小骨という音の増幅装置に転用してしまいました。いまさら顎なしの口というわけにもいかないので、再び「上顎は方形骨ならぬ鱗状骨(リンジョウコツ)、下顎は間接骨ならぬ歯骨(シコツ)」(遠藤)で顎の蝶番を確保したと考えられています。約3億7000万年前に舌顎骨(ゼツカツコツ)をアブミ骨に、約2億年前に方形骨をキヌタ骨、さらに鱗状骨を上顎、歯骨を下顎に変化させて、私たち哺乳類の顎ができあがったようです。
まったくもって、進化とは場当たり的でいい加減なものだと感じますが、呼吸器(鰓)を咀嚼器(顎)に転用したと思ったら、最後に聴覚器(耳小骨)に変えてしまうという荒技に改めて驚かされます。さて、ようやく開閉式の口にたどり着いた私たちですが、「食べる」という行為を担う「口」に必要なものがまだ足りません。さて、次に何が出てくるのか、楽しみにしてください。