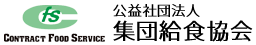vol.9
肉食のタブー ~「食べる」という行為の意味⑥
ナマコのコリコリとした歯ごたえは、酒の肴にうってつけです。沖縄のリーフに転がっているナマコを見たときには、最初にコレを食べようと思った人はすごい! と思いました。古代中国の伝承に「神農」と呼ばれる人が登場します。
木材で農具を作り、土地を耕して種を蒔き、農耕することを人々に教えたと言われています。また、自らありとあらゆる草を嘗めて、薬効と毒性の有無を検証したとも言われています。おそらく、古代の多くの人々による経験と実験、さらに犠牲によって得られた知恵や知識が「神農」という一人の人格で表現されているのだと思われます。植物であれ、動物であれ、ソレが食べられるのか、毒なのか、薬なのか、は食べてみなければわからなかったでしょう。あるいは他の動物が食べているものを食用または薬、避けるものを毒と判断したのかもしれません。もっとも、「そば清」という落語の演目にあるように、そばの大食いを自慢する男がウワバミ(大蛇)の食べた薬草(蛇含草)を飲んだところ、自分(人間)を溶かす薬草であった、などという間違いもあったでしょう。
こうした試行錯誤を繰り返しながら、食用・薬用・毒物などを選り分けてきたに違いありません。
問題は、その成果をどのように後世に伝えるのか、という問題です。中国最古の本草書とされる『神農本草書』のように文字に残すという方法も考えられるのですが、いま一つの方法として「タブー」という形で伝えることもあったのではないでしょうか。
例えば、肉食がなぜタブー視されやすいのか。①人間にとって価値ある食物であるからこそ社会的規則としてのタブーの効果がある、②人間にとって心理的に近く感情移入して殺すことに抵抗感を感じる、という理解があります(石毛直道、食事の文明論、1982年)。
米と菜食を中心とする日本的な食事が確立する背景には、仏教思想や肉食を「汚れ」とみなす日本人の肉食禁忌の観念があると言われてきました。しかし、日本で最初の肉食禁止令となる「天武の殺生禁断令」(675年)は漁撈への従事とウシ、ウマ、イヌ、サル、ニワトリの肉食を禁じているものの、禁止期間を農繁期に限り、それ以外の肉食を禁止しないとの但し書きがついています(鵜沢和宏、肉食の変遷、2008年)。つまり、農繁期の(主に家畜の)肉食を禁止することで農業生産への集中を促すとともに、日本の最も代表的な狩猟動物であるシカとイノシシが抜け落ちていることから、「肉食そのものを強く禁じる意図がなかった」と考えられています。そもそも何度も繰り返し殺生令が出されたという事実(12世紀初頭までに11件の殺生令が出された)そのものが、禁令にもかかわらず日常的に肉食が行われていたことの裏返しであり、ほぼ家畜家禽に限定されていることが、野生動物の肉食を裏付けているのです(原田信男、中世における殺生観の展開、1995年など)。
さらに、中世・近世においても、人の残飯を漁る都市型の野生動物ともいえる野良犬が捕獲され、食用とされていた事実が、「栄養不足を補う日和見的な狩猟の一形態」であるとみなされます。
「魏志倭人伝」には「其地無牛馬豹羊鵲」との記述があります。つまりこの時代には、日本にはまだ牛や馬はいなかったと考えられ、馬は牛よりも先に渡来したようです。遺伝学的調査によると、日本の家畜馬は、朝鮮半島経由で渡来人によって運ばれたと考えられています。故に畜舎の「ウマヤ」はあっても、「ウシヤ」と呼ばれるものは聴いたことがありません。牛が初めて歴史に登場するのは大和時代の前期(4~7世紀)になってからで、平地で放牧された牛は、5世紀末には既に野を覆う程だったと云われています。
しかしながら…
弥生時代までにもたらされた動植物の生産活動のうち、稲作を柱とする植物生産(農耕)だけが後世まで残り、動物資源の生産(ブタ飼育)は古代以降、次第に低調となって、やがて姿を消してしまう。
(鵜沢和宏、肉食の変遷、2008年)
なぜ、日本社会に畜産が定着しなかったのかという理由について、①山地が多く、密集して生える森林に邪魔され、効率的な牧畜を営む自然条件に恵まれなかったこと、②豊富な水産資源で不足する動物性タンパク質を補うことができたこと、などのように、合理的な判断があったとの指摘もあります。つまり、肉食禁忌は「仏教的罪悪感や汚れといった意味体系と、日本の生態環境で肉食生産を行うことの非効率性とが合致した結果」(鵜沢和宏)であると考えられるのです。
とはいえ、人間が動物を食べるという行為には、動物を殺すというある種の後ろめたさが付きまといます。動物を殺すことの罪悪感を解消・軽減するために人は、①動物を神の賜物とみなす文化(供犠の文化①/②)、②殺した動物の霊を弔う文化(供養の文化)、の2つの方法をとってきました(中村生雄)。この「供養の文化」こそが、日本の動物観、自然観の特徴であると考えられてきました(藤井弘章、動物食と動物供養、2009年)。食用に供する動物に注目すると、供養塔を建立する場合と供儀目的に儀礼を行うだけの場合(マタギの儀礼)とがあります(山根洋平、動物供犠における人間と動物との関係から導かれる宗教性、2014年など)。
食事の文化にはさまざまな宗教的・文化的なタブーがつきまとっているといわれます。イスラム教に関わる「断食月の昼間は飲食しない」「ブタ肉は食べない」「イスラム教徒の屠殺した動物以外の肉を食べてはならない」などの食物のタブーはとりわけ有名です。東アフリカのタンザニアのある村には、文化や部族の違いによる食物のタブーや料理法のタブー、食べ方のタブーなど、さまざまな食事のタブーがあるそうです(石毛直道、食事の文明論、1982年)。狩猟・採集民のハツァピ族は、クサムラカモシカなどの大動物の心臓、胸の一部、肩と首の部分、内臓の一部を「神の肉」として男にだけ食用が許され、女子どもにはタブーとされています。牧畜民のダトーガ族と半農半牧民のイラク族は、多くの牧畜民と同様に、魚を食べることがタブーとされます。また、ダトーガ族はウシの肉を食べるときに、仇敵のマサイ族が焼いて食べることを理由に、煮て食べなければなりません。マサイ族でも、肉を煮て食べるのは女の料理法であるとして、男の料理である焼肉は女から離れた屋外でつくられ、食べなければなりません。スワヒリと呼ばれる農耕民の中のイスラム教徒は、畑を荒らすイボイノシシを殺しても、イスラム教が禁じるブタとみなして食べることはありません。ハツァピ族はヘビを食用にすることがあるのですが、スワヒリには嫌悪感を感じさせます。
このように、「タブー」という形には多様な意味が含まれており、一概に肯定したり、否定したりできないものであることがお解りいただけるのではないでしょうか。