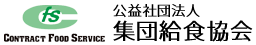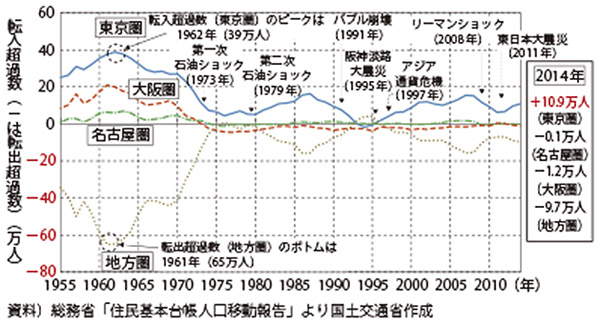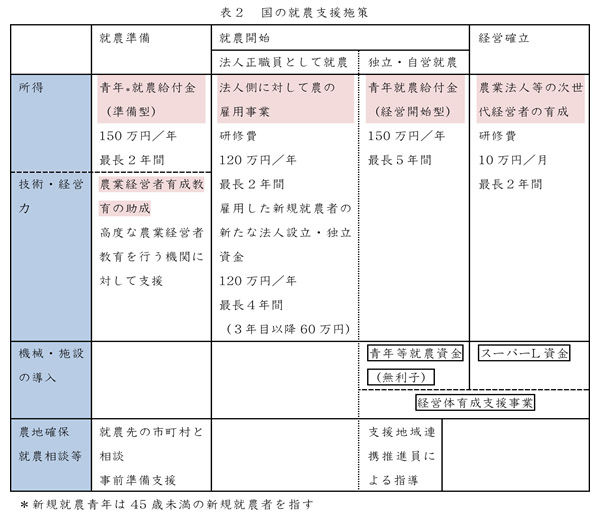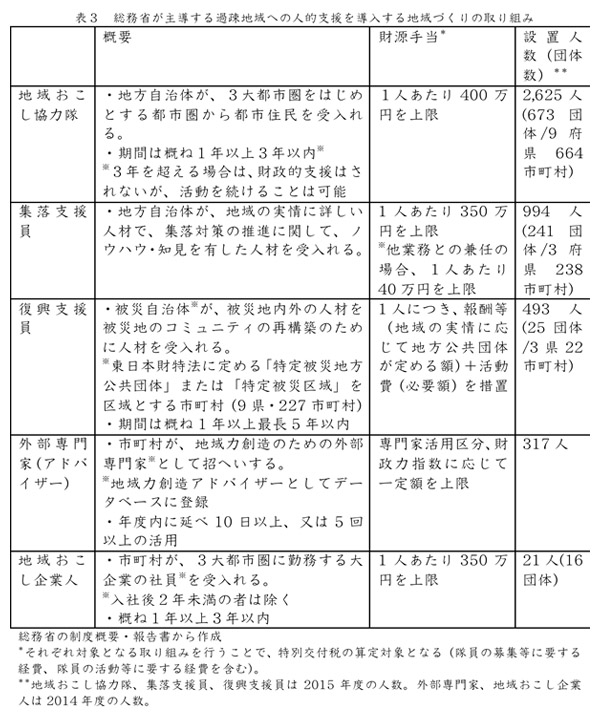vol.15
食育基本法と学校給食 ~食育と地域づくり⑤
食育基本法と食育推進基本計画
食育基本法という法律があります(図)。2005年に成立したこの法律は、内閣府に食育推進会議を置き、内閣総理大臣を会長に食育担当大臣他12省庁の閣僚を委員として、国家レベルで国民の食の問題に取り組もうとする異例のものです。その後、内閣の重要政策に関する統合調整等に関する機能の強化のための国家行政組織法等の一部を改正する法律(2015年)によって、会議を農水省に、会長を農水大臣に変更して進められています。この法律の目的は「現在及び将来にわたる健康で文化的な国民生活と豊かで活力ある社会実現に寄与すること」(第1条)とされ、 7つの基本理念(第2条〜第8条)を設定しています。その後に、「関係者の責務」(第9条〜第13条)、「法制上の措置及び年次報告書」(第14条〜第15条)、「食育推進基本計画等」(第16条〜第18条)、「基本的施策」(第19条〜第25条)、「食育推進会議等」(第26条〜第33条)と続きます。このうち年次報告書に当たるものが「食育白書」と呼ばれるものであり、閣議を経て国会に報告されています。また、食育推進基本計画が2006年度から5年ごとに作成され、現在は第3次食育推進計画(2016年〜2020年)です。この計画は国の他に、都道府県食育推進計画(第17条)、市町村食育推進計画(第18条)の策定が求められています。
学校、保育所等における食育の推進
7つの基本的施策の中に「学校、保育所等における食育の推進」という項目が設定されており、学校給食における取り組みも主にここに位置づきます。学校給食に関連する制度の見直しが行われる中で、栄養教諭制度の導入(2005年)とともに、学校給食法の改正(2008年)によって給食の目的として「学校における食育の推進」が付け加えられました。2018年5月1日現在で、全都道府県に6324人の栄養教諭が配置されており、「栄養教諭を中核としたこれからの学校の食育」がまさに食育推進の鍵であると認識されています。他方で、学校給食は増加しつつあり、2018年5月現在、小学校で1万9453校(全小学校の99・1%)、中学校で9112校(全中学校の89・9%)、特別支援学校等も含む全体で3万92校が学校給食を行い、約950万人の子ども(完全給食を受けている児童・生徒の割合は90・5%)が給食を食べています。こうした流れの中で学校給食への「地場産物食材」の使用が模索されており、2015年度の時点で26・9%(2005年から5%増加)となっています。ちなみに、国産食材の使用割合は77・7%でした。
食育白書(2016年度)は、「地場産物を学校給食に活用し、食に関する指導の教材として用いることにより、子供が、より身近に、実感を持って地域の自然、食文化、産業等について理解を深め、食料の生産、流通に当たる人々に対する感謝の気持ちを抱くことができます。また、流通に要するエネルギーや経費の節減、包装の簡素化等により、環境保護に貢献することもできます。 さらに、地域の生産者等の学校給食をはじめとする学校教育に対する理解が深まることにより、学校と地域との連携・協力関係の構築にも寄与しています。 このような効果を期待して、各地の学校給食で地場産物の活用が推進されています。」と述べています。
「おふくろの味」を子どもたちに伝える試み
基本的施策のうち「地域における食生活の改善のための取組の推進」(第21条)と「食文化の継承のための活動への支援等」(第24条)に当たる事例が、新潟県聖籠町の食生活改善推進協議会の実践です。協議会のメンバーは、『聖籠の食文化をたずねて』(1998年)をもとに聖籠中学校で授業を行いました。新潟市の郊外にあって地域の構造が急速に変化し、長く受け継がれてきた地縁や血縁のつながりが崩れつつある中で、保健師による「町のこどもたちの体の実態調査」の結果から住民の「食」に対する考え方の変化が明らかになりました。5年間にわたる保護者との勉強会や懇談会、講習会を通じて、それが「子どもの食に無関心な母親」の問題ではなく、「食生活に関する世代間の伝承の不足」による問題であることに気づきました。そこで、町に伝わる食を探るために、町の古老への聞き取り調査を行いました。聞き取りは生産と消費を結びつけて考えること、生活により密着した形での食を聞き取ることに成功したのです。その成果として刊行されたのが、『聖籠の食文化をたずねて』です。この本名は単なる伝統食のレシピ集ではなく、地域の自然条件や農業・漁業、伝統行事、住居などのすべてが「食」と密接に関わっていることが浮き彫りにされていた。この本をテキストに、中学生たちは地域の食文化の歴史を「町のおばさん」という生きた教材から学んでいったのだ。次第に生徒の反応は変化し、食への態度も変化した。
『新潟県公民館月報』2014年12月号に、手嶋勇平さん(元聖籠町教育長)も聖籠町食生活改善推進協議会の実践を伝えています。「聖籠町食生活改善推進協議会のオバさんたちも思い込みを。今の若い母親が子どもに与える食内容への危機感から、食の実態調査を実施し、その結果からの問題点を母親に指摘しても入らなかった。その背景を話し合い、地域の食文化をオバさんたち自身がつかんでいなかったことに気づく。そして、それをまとめるプロジェクトが立ち上がり、公民館主事として私も参加した。研究者の指導で、昭和10年代の地域性ある生活を語れる高齢者からの聞き取りが始まった。オバさんたちにとって文章化は容易でなかったが、高齢者の生き生き語る姿に励まされ、3年越しで『聖籠の食文化をたずねて』が刊行された。その発刊祝賀会で喜びのオバさんたちへ 会場から提案が上がった。『刊行の動機を聞けば、子どもの食への心配からとか。であれば、刊行は子どもにその内容を返す出発点ではないか』と。オバさんたちは喜びから緊張へシフトを。その後、その本をテキストに中学校に入り、生徒と交流学習を続けている。学校に総合的学習が導入される前のこと。批判からは一歩が始まらないことを実感したオバさんたちだった。」
センター方式でも食育・地産地消を目指す奄美市の挑戦
こうした取り組みが進む中で、鹿児島県奄美市では旧名瀬市と旧住用村にある小学校・中学校18校の給食施設を廃止して2019年度から学校給食センター方式に改め、そこで食育・地産地消の取り組みを進めようとしています。(『学校給食に連動した地産地消・食材流通による地域活性化に関する調査研究』)奄美市内の両地区にある小学校・中学校はそれぞれ自校方式の給食施設をもっているものの、築24〜40年(築30年以上が59%)と改修時期を迎えつつあり、約50食以下(53食〜17食)の提供が9校を占めています。他方で、児童・生徒数の減少や学校給食法の改正による衛生管理基準の強化などへの対応を求められていることで、センター方式への転換を決めました。1日4000食(1回2000食)をまかなう食材を地産地消で確保し、すべての学校での食育を進めるのは容易でないことは明らかです。市内の農家数は高齢化・減少傾向にあり、さとうきびやトロピカル・フルーツへの生産に大きく偏っています。一つの可能性を示しているのが、飛び地合併となっている旧笠利町の笠利学校給食センターの取り組みです。毎日600食を提供しているセンターは、地元の農家から食材の供給を受けながら地元食材の比率を高めて子どもたちに工夫した給食メニューを提供しています。こうした取り組みを支えているのが、仲介する地元の生活研究グループの女性たちが設立した合同会社・味の里かさりの存在であり、市内でも農地と農家が多くあるという条件等です。笠利給食センターをモデルとして、新給食センターも市内—大島内—奄美群島内—県内と同心円的に地元食材の割合を設定して少しずつ地元比率を高めるために地域農業の育成を図るとともに、高齢者への給食の提供も検討する必要があります。また、食材を調達する地元組織を育成することで、栄養教諭や栄養士・調理員と協力した食育を進めることも期待されています。
最後に、奄美市にも地元の食材を使い、障害をもつ人たちを雇用してレストラン等を経営する社会福祉法人・三環舎のような団体があります。学校給食の調理や加工に、こうした団体の参加を求めることも地域の持続可能性を考える上で重要な要素でしょう。
朝岡幸彦(あさおか ゆきひこ / 白梅学園大学特任教授/元東京農工大学教授)